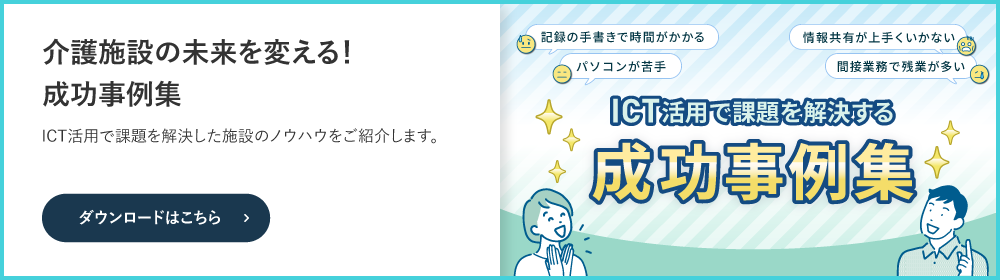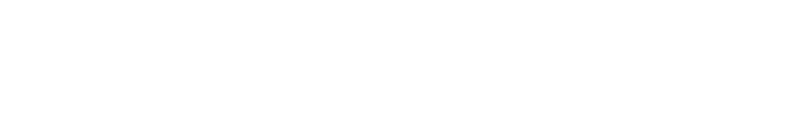
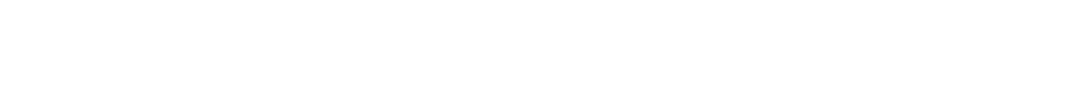
-
介護記録の基本的な書き方
-
2018/09/19
-

-
介護保険法の指定または許可を受けた介護施設、事業所では、提供した介護内容を具体的に記載した介護記録を作成し、一定期間保管するよう義務づけられています。万が一、実際に提供した介護内容と記録内容が合致していないなどの不備が、監査などで明らかになった場合は、介護報酬の返還や施設、事業所指定の停止、または取消処分を受ける恐れがあるため、介護記録の基本的な書き方や手順をしっかりと身につけておくことが大切です。ここでは、介護記録の基本的な書き方を解説します。
介護記録は何に、どうやって記載する?
ほとんどの施設や事業所で、紙の記録用紙に記載するアナログ式の方法を採用しています。介護記録に記載をする際、鉛筆ではなくボールペンを使用するため、誤字や脱字がないよう慎重に記載しなければいけません。 もちろん、修正テープや修正液の使用は厳禁です。修正したい場合は、空欄に修正者の署名とともに修正内容を記載するようにします。メモ帳を頼りに介護記録を作成する
介護の現場では、介護記録を記載しようとペンを取った瞬間に、記載しようと思っていた大切な出来事を忘れてしまっていることも少なくありません。また、記憶が曖昧になってしまうと、不正確な介護記録になってしまいます。 正確な記録を効率よく記載するためには、印象的な出来事や重要な変化に気づいたら、その都度メモを取り、介護記録に反映させるようにしましょう。介護記録の基本的な書き方
護記録は、単に提供した介護サービスを羅列するのではなく、利用者の生活状況や心身の状態のほか、より良い介護が継続的に提供されるために必要な情報を記載しなければいけません。慣れないうちは大変負担の大きい作業ですが、以下に挙げるような基本的な書き方や手順さえ身につければ、比較的スムーズに記載できるようになります。5W1Hを活用する
5W1H(いつ、誰が、どこで、何を、なぜ、どのように)は、介護記録を記載する上で欠かせない要素です。書きたい内容をイメージできていても、うまく文章にまとめられないというときは、5W1Hの要素を一つひとつ順を追って挙げていくと、簡潔に記載できるでしょう。客観的な事実を記載
介護記録には、客観的な事実(情報)のみを記載するのが原則です。担当した介護者(=記録者)の気づきや意見、推測を混同させると、他者に伝わりにくい記録になってしまいます。もし、今後の対応を検討する上で必要な意見を記載したい場合は、別枠に分けて記載するようにしましょう。曖昧な表現は避ける
「~かもしれない」、「~したようだ」、「おおむね良好」などの曖昧な表現は、利用者の変化を把握する上で支障を来します。実際に観察された出来事のみを記載するのはもちろんのこと、程度を記載する際は、数値や尺度を用いて具体的に記載するよう心掛けましょう。専門用語は使用しない
介護記録は、利用者やそのご家族が読んでも理解できるよう記載する必要があります。そのため、説明の難しい略語や医療専門用語は、できるだけ使用しないように注意します。簡潔にしすぎない
介護記録は、できるだけ簡潔にまとめておきたいものですが、あまり簡潔過ぎるのも問題です。実際に提供した介護の内容、利用者の反応のほか、その過程における介護者の働きかけ(判断)やその根拠なども記載しておくと、より利用者の状態が伝わりやすくなります。 限られた時間の中で、正確かつ分かりやすく記録を記載するには、観察すべきポイントをしぼって、利用者に接することも重要になります。介護記録は、介護従事者にとって切っても切り離せない業務のひとつなので、しっかりと基本事項をおさえておきましょう。当コラムは、掲載当時の情報です。
最後までお読みいただきありがとうございました。介護事業所様にお役立ちいただけるよう「お役立ち資料」をご用意しました。是非、ダウンロードしてご活用いただければと思います。ダウンロードは無料です。