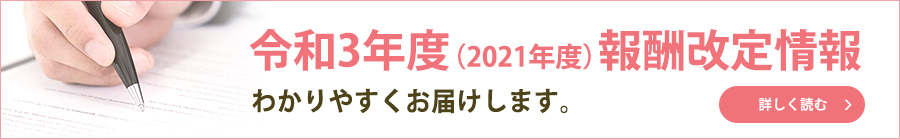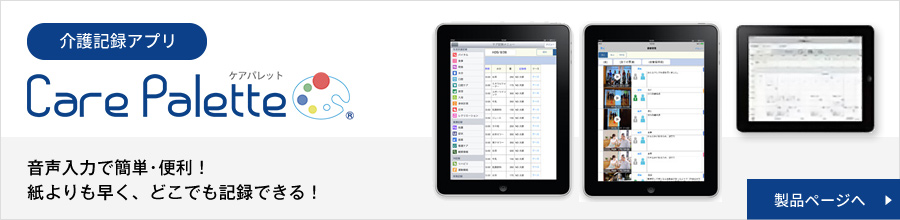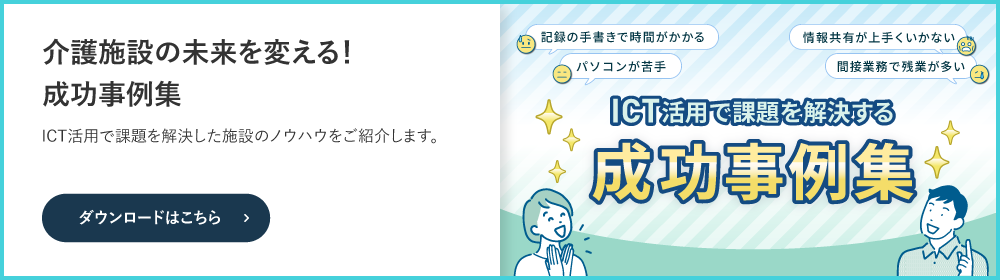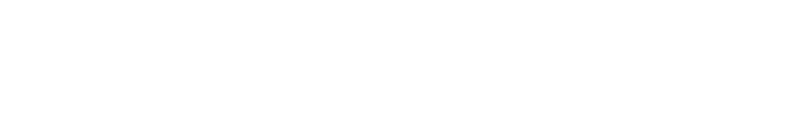
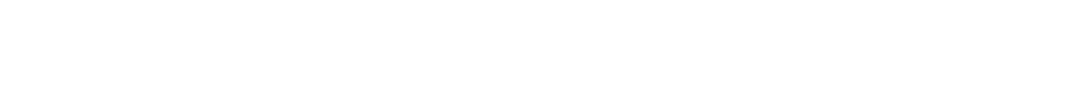
-
介護の現場では「介護記録」が重要!
書き方と便利なツールを紹介 -
2020/04/16
-

-
介護の現場では、提供したサービスを記録するという「介護記録」が必須です。介護記録は、自分たちが提供したケアの証明になります。また、スタッフ間で統一されたケアを行うためにも介護記録は大きな意味を持っています。
ですが、「何を書けばいいか分からない」「どのように書けばいいか分からない」「介護業務と並行して介護記録を残す時間がない」といった話が非常に多く聞かれます。そのため、適切な介護記録が残せていないケースもしばしば見受けられます。介護記録はなぜ必要なのか、どう書けばいいのか、介護記録を楽に書く方法はないのかをお話しします。
介護記録とは
まず、介護記録には様々な種類があります。
・利用者の名前や住所、疾患や介護度、家族構成などが書かれている「フェイスシート」
・利用者の現在の身体状態や能力などの情報を収集分析し、ケアの目標を明確にする「アセスメントシート」
・目標達成に向けてスタッフが提供する介護の計画を定めた「介護計画書」
・介護計画書に沿って提供された介護の実践を記録する「介護経過記録」
・体温や脈拍、食事や排せつといった日常の状態を記録する「日常介護記録」
・事故やトラブルの内容を記録した「事故報告書」
などです。事業所によって介護記録の呼び方は様々ですが、どこの事業所でも同様の目的で介護記録を用います。
★オススメ特設ページ
介護記録はなぜ必要か
 たくさんの種類がある介護記録ですが、なぜ必要なのでしょう。 大きく分けて3つの理由があります。
たくさんの種類がある介護記録ですが、なぜ必要なのでしょう。 大きく分けて3つの理由があります。
チーム間の情報共有のため
介護現場には必ずチームが存在します。それは事業所の中のスタッフの場合もあれば、事業所単位で一人の利用者のケアにあたる場合もあります。それぞれのスタッフが行ったケアは、チーム全体にはなかなか伝わりません。
そうなると、利用者に対して一人ひとりがバラバラの介護を提供してしまうことになり、ケアの一貫性は失われてしまいます。利用者に効果的な介護を行うためにも、チーム間で「ケアの目標は何なのか」「どのような介護を行うのか」「利用者の状態はどうなっているのか」などの情報を共有する必要があります。そのために介護記録は大きな意味を持つのです。
根拠に基づいて意図的な介護を行うため
介護の実践とは、計画に沿って適切な介護を提供することです。そのためには「なぜこの介護方法なのか」を明確にする必要があります。それに必要なのが先述した「アセスメントシート」です。利用者がどのような生活を送りたいか、その希望を叶えるためには利用者がどういう状態になることを目指すのかといった生活課題を分析し、目標を定めます。そして目標達成に向けた介護を「意図的に」提供するのです。
ひと言で介護スタッフといっても、それぞれに経験年数や入職時期が違います。そのため「なぜこの介護方法なのか」が明確に介護記録として残されていないと、理由が分からないまま介護を提供する職員が出てきてしまいます。場合によっては自分勝手な介護を始めてしまうことも。そうなると利用者の目標達成はどんどん遠ざかることでしょう。
利用者に行うケアの目的・根拠を明確にし、すべてのスタッフが同じ目的意識を持ってケアにあたるためにも介護記録は必要なのです。
提供したサービスの証拠を残すため
介護現場では、時に自分たちがどのような介護を行ったのかを証明する必要があります。その相手は利用者の家族であったり、介護保険課であったり、市町村の場合などもあります。 その際にいくら口頭で説明したとしても、それには一切の証拠能力がありません。仮にどれだけ適切な介護を提供していたとしても、介護記録がないとそれは提供していないのと同じ意味になってしまいます。自分たちが行ったケアの正当性を証明するためには、提供した介護を適切に介護記録に残すことだということです。
★オススメ商品
介護記録の書き方とは?
介護記録の書き方にはいくつかの留意点があります。適切な介護記録を残すためには覚えておきましょう。
5W1Hを意識して書く
5W1Hとは①いつ(WHEN)②どこで(WHERE)③誰が(WHO)④なぜ(WHY)⑤何を(WHAT)⑥どのように(HOW)のことです。これらを意識した介護記録を書くことで誰が読んでも分かりやすい内容にすることができます。つまり、5W1Hを意識した介護記録の書き方とは、客観的な記録として書くということです。
主観や思い込みで書かず、事実を書く
「~と思われる」といった書き方はあくまでもスタッフ個人の考えになってしまいます。また、レクリエーションなどの介護記録として「楽しんでいた」といった書き方は利用者に楽しんでいたのかを確認したうえで書かないと、職員が「楽しそうに見えた」という思い込みに過ぎない記録となってしまいます。
介護記録に求められるのは客観的事実のみです。もし「~と思われる」「~と考えられる」という主観を交えた記載が必要な際は、そう考えるに足りる根拠も併せて記録する必要があります。
必要なことだけを書く
介護記録に残すべき最低限の内容は、「計画に沿ったケアの記録」「経過を観察している事象の記録」「介護をしていて気になった点の記録」などが考えられます。逆に言えば、それ以外の介護記録を残すことはさほど重要ではありません。必要な記録だけを過不足なく書けるようになれば、質の高い介護記録が残るようになるでしょう。チーム内で、どのような記録に絞って書くのか、書き方のルールを定めるのもいいかもしれません。
介護記録が現場の負担になっている?
適切な介護を行うために必要不可欠な介護記録ですが、実際に利用者のケアを行いながら利用者全員の介護記録を残していくことは容易ではありません。場合によっては業務時間終了後に介護記録を書くといった慣習になってしまっていることもあります。介護記録を残すことが重荷になり、早く終わらせたいがために質の低い介護記録を適当に書いてしまっては、元も子もありません。
質の高い介護記録を残しながらも利用者ともしっかり向き合える、そんな方法が求められているのです。
介護記録を楽にする方法
現場の負担になっている介護記録ですが、質の高さを維持しながらも楽にする方法。 それはIT化です。 IT化して効率化を図れば、煩雑な介護記録の大部分が非常に楽になります。その結果利用者に向き合える時間も確保でき、スタッフの心にも余裕ができます。必然と質の高い介護につながっていくことが期待できます。
しかし現在、電子カルテなどを導入している事業所は多くみられますが、紙媒体に書いた介護記録を改めて電子カルテに入力…という二度手間をしてしまっているところも見受けられます。手書きが必要な介護記録はどうしても出てきますが、無駄な労力は削るに越したことはありません。今後も介護の需要が高まる今こそ、効果的にIT化を進めることが現場に今求められている改革といえるかもしれません。
介護記録を効率化する!おすすめのツール
介護現場の業務や介護記録を残す作業を円滑に進めるためにおすすめのツールを紹介いたします。
Care Palette(ケアパレット)

Care Paletteは、TERUMOやNISSEIの体温計、血圧計、パルスオキシメーターと連動しそれぞれの利用者の測定結果を転送、自動で記録するというスグレモノ。 従来は一覧表に書き、それをパソコンに入力といった対応でしたが、大部分の労力の削減が期待できます。
その他の介護記録もタブレットに直接入力することでペーパーレスを図ると同時に、管理が非常にしやすくなります。 さらに、利用者個々に作成された介護方針である「ケアプラン」をタブレット画面で参照することができるのです!すぐに確認できる環境ができれば、介護経験の浅い職員も質の高い介護を提供することができるでしょう。
もう一点、Care Paletteの長所は『外国人スタッフに特化した機能が充実』であることがいえます。 難しい専門用語の逆引きや翻訳、画面表記のひらがな化が可能など、日本語に不慣れな外国人スタッフが介護現場に馴染めるよう配慮された機能は大変うれしいですね。
ほのぼのTALK++

ほのぼのTALK++(ほのぼのトーク)は、iPhone、iPod、iTouchをインカムとして使えるツールです。 介護現場ではしばしばどこにいるのか分からないスタッフを探す時間があります。そんな時もほのぼのトークを使ってマイクで全スタッフに一斉に呼びかけることができ、無駄な時間を大幅にカットできます。他にも気になることを報告する、伝達事項の連絡、分からないことを相談するといった報・連・相もマイクに向かってしゃべるだけ。さらに音声が届くだけでなく話した内容は文字としてデバイスに残すことが可能! 聞き逃した話、もう一度聞きたい話を確認できるのはとてもありがたい機能ですね。職員間の情報共有を円滑化することで業務時間の確保と介護の質を上げることが大いに期待できるでしょう。
★オススメ商品
まとめ
介護記録は質の高い介護を提供し、その根拠を残すために必要不可欠ですが、その一方で業務に負担がかかるものです。適切な書き方を覚えるとともに便利なツールを活用することで介護記録を活用できるものにすれば、まさにスタッフも事業所も、さらには利用者にも有効といえるものでしょう。
当コラムは、掲載当時の情報です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
介護事業所様にお役立ちいただけるよう「お役立ち資料」をご用意しました。是非、ダウンロードしてご活用いただければと思います。ダウンロードは無料です。


介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

その後、介護保険外サービスを運営。その傍らで初任者研修、実務者研修の講師としても活動中。