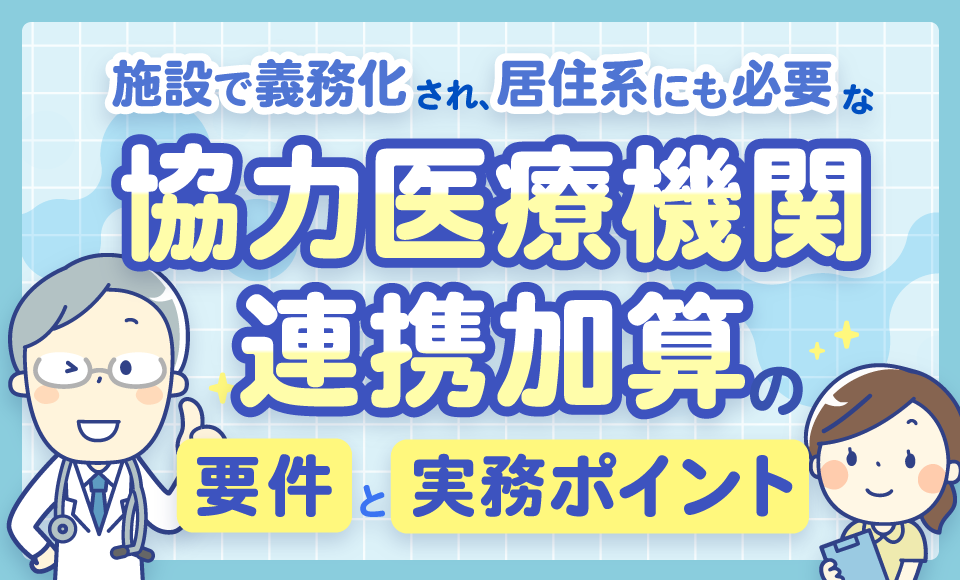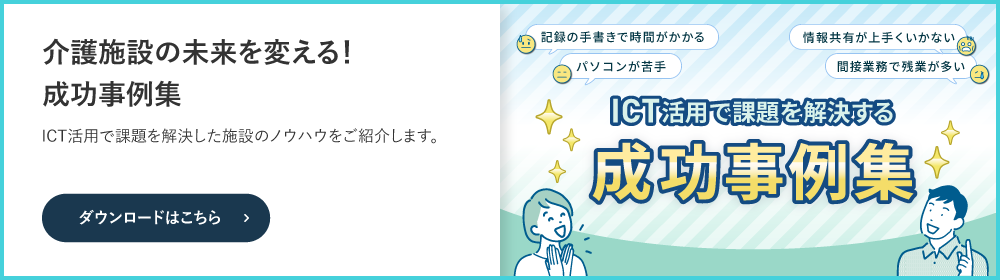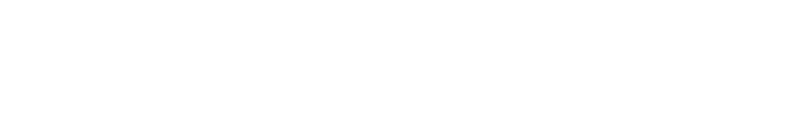
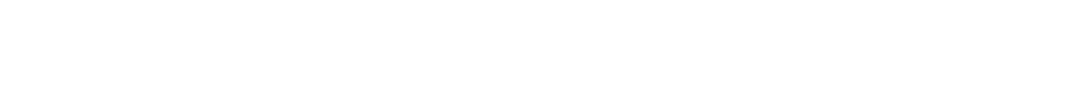
-
【成功事例】ADL・BADL・IADL向上への取り組みとケアの質向上
-
2025/10/17
-
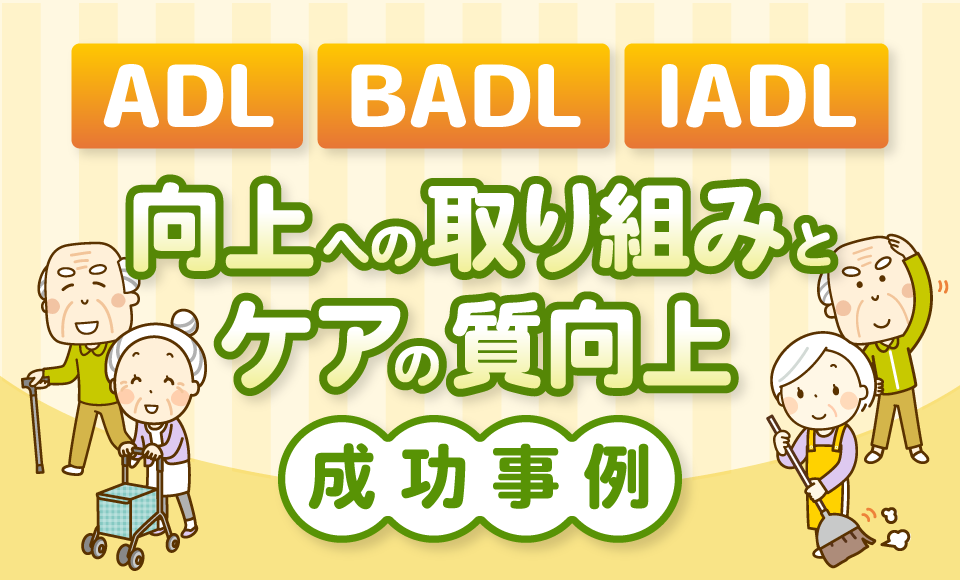
-
「稼働率が上がらない」「スタッフの離職が続く」。これらは多くの介護施設が抱える悩みと言えるでしょう。その解決の鍵のひとつとなるのが、利用者の日常生活動作を示す「BADL」「IADL」の向上です。
日々のケアがなぜ施設経営の安定にまでつながるのか?
この記事では具体的な成功事例をもとに、BADL・IADLへの取り組みがケアの質を高め、稼働率の向上や加算取得を実現するプロセスを分かりやすく解説します。施設運営を安定させるための参考になるので、ぜひ最後までご覧ください。
ADL、BADL、IADLとは
ADLとは、日常生活動作と呼ばれ、生活の基本となるBADLと、より応用的なIADLに大別されます。利用者の自立度を正しく評価し、これらの能力を維持・向上させることが、加齢による心身の衰え(フレイル)の予防につながります。
ADLについてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
「ADL」「IADL」の違いと自立支援のケアのポイント(1)BADLとは
BADLは基本的日常生活動作のことで、食事や排泄、入浴、更衣、移乗といった、人が生きていく上で最低限必要な身の回りの動作を指します。いわば生命維持の土台となる基本的な能力です。業務のなかで時間に追われていると、利用者ができることでもつい手伝ってしまうこともあるでしょう。しかし、安易なお手伝いはその方の残っている力を奪ってしまうリスクもあります。日々のケアのなかで、本人のできることを維持できるよう支援していくことが介護職員には求められています。
IADLとは
IADLは手段的日常生活動作のことで、買い物や食事の準備、洗濯、金銭管理といった、より複雑な応用動作を指します。BADLの次の段階にある応用的な動作で、社会的な生活を送るための手段となる動作です。ADLの低下は、このIADLから始まることが多く、フレイルの進行を予測するサインになります。調理や掃除といった役割を担ってもらうことで、IADLの維持やフレイル予防につながります。

BADL、IADLの向上に取り組むメリット
BADL・IADLの向上は、利用者の生活を豊かにするだけではありません。職員の働きがいを高め、施設経営を安定させるという好循環を生み出します。ここでは、その具体的なメリットを3つの視点から解説します。
ケアの質が安定し、離職率が低下する
「利用者のADLを向上させる」という共通の目標をチームで掲げることは、職員一人ひとりのケアに対する意識を統一し、サービスのばらつきを減らす効果があります。「どうすれば〇〇さんが自分で食事を摂れるようになるか」といった前向きな情報共有や話し合いの場が自然と増え、チーム全体の関係性も向上するでしょう。
介護労働安定センターの調査では、離職の最大の理由は「職場の人間関係」とされています。ADL向上への取り組みを通じて良好なチームワークが醸成されれば、職員が定着しやすい環境になります。結果として経験豊富なスタッフが揃うことで、施設全体のケアの質が安定するという、理想的な好循環が生まれます。
利用者のQOLが向上し、稼働率が安定する
BADLやIADLの向上は、利用者の生活に「自分でできること」を増やし、QOL(生活の質)を直接的に高めます。食事や掃除といった日々の活動は、心身機能の活性化を促し、フレイルの進行予防に役立ちます。利用者が健康でいられる期間が長くなれば、予期せぬ体調不良による入院や退所のリスクが減少します。
その結果、空床期間が短縮され、施設経営の根幹である稼働率が安定します。利用者のQOLが上がるケースが増えると、地域からの評判もよくなり、新たな入居希望者の獲得という面でも、施設の大きな強みとなるでしょう。
施設運営が安定し、さらなる加算取得を目指せる
職員の定着と高い稼働率は、施設の収支を安定させ、健全な運営基盤を築きます。この安定した基盤があると、より質の高いケアの提供と収益の向上を目指す「加算取得」が現実的な目標となります。
ADL向上の取り組みによって算定できる可能性がある加算は以下の通りです。
- ADL維持等加算
- 科学的介護推進体制加算
- 生活機能向上連携加算
- 自立支援促進加算
- 排せつ支援加算
- 経口維持加算
- 経口移行加算
質の高いケアが収益として正しく評価されることで、職員への還元や設備投資といった次の展開も可能になり、施設全体の成長を後押しします。
BADL、IADLの向上に取り組んだ成功事例
ここでは、BADL・IADLへのアプローチが、利用者と施設の双方に良い変化をもたらした事例を3つ紹介します。日々のケアにおける一つひとつの工夫や改善の積み重ねが利用者のADL向上につながり、ADL維持等加算などの取得につながるため、参考にしてください。
【事例1】本人の身体機能を見誤っていた
肺炎で入院後、食事もままならず看取り目的で退院されたAさん。当初は寝たきりでお話しされることもありませんでした。しかしある夜勤中、かすかな声で「トイレに行きたい」と訴えがあり、もう一人の夜勤者と半信半疑でトイレに誘導すると、しっかりと排尿がありました。そして、笑顔で「ありがとう」と言ってくれました。
翌日には「起きたい」「お腹がすいた」といった要望も発言するようになったため、離床や食事摂取を再開しました。
この出来事を機に、入院中の情報だけを鵜呑みにせず、ご本人の今の力を把握する努力をすることで、残っている機能を奪わずに済むことを学びました。
【事例2】IADLに働きかけ落ち着きをとりもどした利用者
食後の忙しい時間帯になると落ち着かずに歩き回り、職員の後を追いかけてくるBさん。不安になるとどんどん興奮してしまう傾向がありますが、いつも一緒にいられるわけではありません。ご家族から「家では家事を生きがいにしていた」と伺ったため、カンファレンスでの検討やご家族からの同意を得たうえで、食後の床の掃き掃除をお願いしたところ集中して掃除をしてくれました。さらに、使ったおしぼりやエプロンを洗濯場に持って行く際に、洗濯カゴを持ってもらうようお願いすると、快く応じてくれました。
この対応を介護ソフトに記録し、他の職員にも同じ対応をしてもらったところ、ご自身の役割を認識されたBさんは落ち着きを取り戻します。食後のソワソワしはじめたころに「掃除の時間になったら呼びますね」「あとで洗濯もお願いします」などとお伝えすると「仕方ないわね」とお茶を飲みながら待ってくれるようになりました。本人のIADLに働きかけたことで、施設全体のケアもスムーズになった事例です。
【事例3】科学的介護情報システム(LIFE)のフィードバックから対応を見直した
厚生労働省が推進する科学的介護情報システム(LIFE)では、利用者の機能の評価をLIFEに情報提供します。事業所は、LIFEに集まったデータを元にしたフィードバックを受け、ケアプランに反映させることで、勘や経験だけに頼らない「科学的介護」の実践を目指します。
実際にLIFEからのフィードバックをもとに、ADLを評価し直したCさんの事例です。LIFEのフィードバックで「食事動作が低下傾向」と示されたCさん。自力摂取はできていたため、職員があまり意識していませんでした。介護記録を見ると確かに半年前ごろから徐々に食事摂取量が低下していました。よく観察すると、スプーンが細く滑ってしまい、食事を口まで運ぶのに苦労していることがわかりました。そこで持ち手の太いスプーンを導入したところ、食事摂取量が改善。LIFEのフィードバックによって気づきを得られた事例です。
成功事例に共通する「記録と情報共有」の重要性
これらの事例に共通するのは、職員が利用者の小さな変化を見逃さず介護ソフトに「記録」し、それをチームで「共有」した点です。なぜなら、BADLやIADL向上の取り組みは、計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Action)を繰り返すPDCAサイクルそのものだからです。特に、どのケアが効果的だったかを客観的に評価し、次の一手を考える「C」と「A」の段階では、信頼できる日々の記録が全ての土台となります。
しかし、その重要な介護記録が手書きの紙やExcelでの管理では、リアルタイムで共有できません。さらに、「記録が重要だと分かっていても、業務の最中に入力まで追い付かない」という、記録業務そのものへの負担感も大きな課題と言えるでしょう。
だからこそ、個人の頑張りに頼るのではなく、組織として一貫したケア改善を実現するために、情報を一元管理できる介護ソフトを導入したり、それを活用する「仕組みづくり」が大切になります。
NDソフトウェアの音声入力システム「ほのぼのVoice」を活用すれば、いつでもどこでも声で記録を残せ、記録の呼び出しもできます。記録の入力負担を軽減し、よりリアルタイムな情報共有を実現することで、チームケアの質をさらに高められます。
まとめ
本記事で解説した通り、BADL・IADLの向上は、ケアの質の向上から職員の定着、そして安定した施設経営に至るまでの好循環を生み出します。そして、その成功の鍵は日々の気づきの「記録」や、チームで「共有」できる仕組みづくりが大切です。
介護ソフト「ほのぼのNEXT」では、ケース記録だけでなく、リアルタイムでの情報共有を可能にし、LIFEと連携したADL維持等加算や科学的介護推進体制加算の算定も効率的におこなえます。ケアの質と経営の安定を両立させるため、ぜひ資料請求をしてお確かめください。
介護・医療経営の専門家が最新のヘルスケア情報を毎月ご提供しています。お申し込みはこちら当コラムは、掲載当時の情報です。
参考URL
健康長寿ネット 自立生活の指標:日常生活動作(ADL)とは
厚生労働省 ADL:Barthel Index
日本老年医学学会 手段的日常生活動作(IADL)尺度
介護労働安定センター 令和6年度介護労働実態調査
厚生労働省 LIFEクイックガイド
厚生労働省 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の報酬・基準について(検討の方向性)

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。