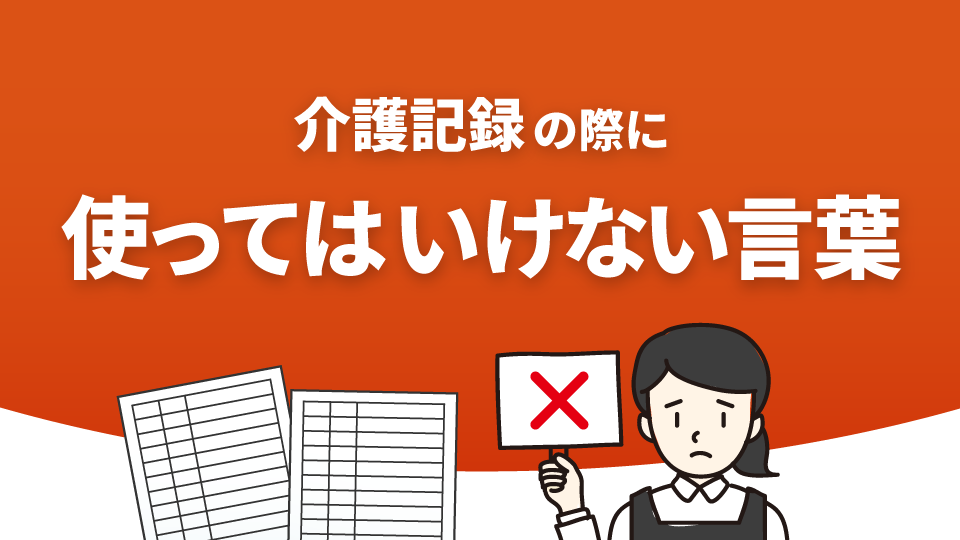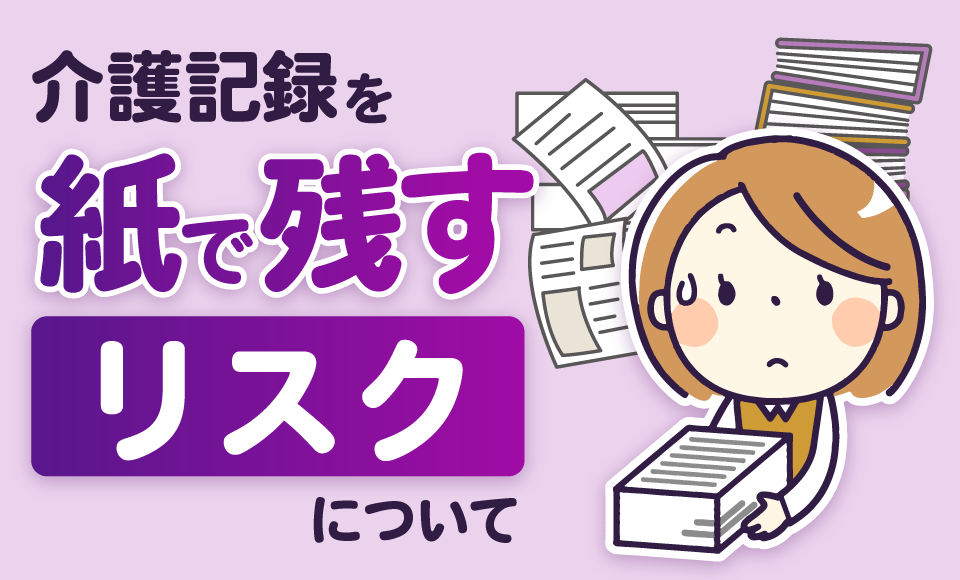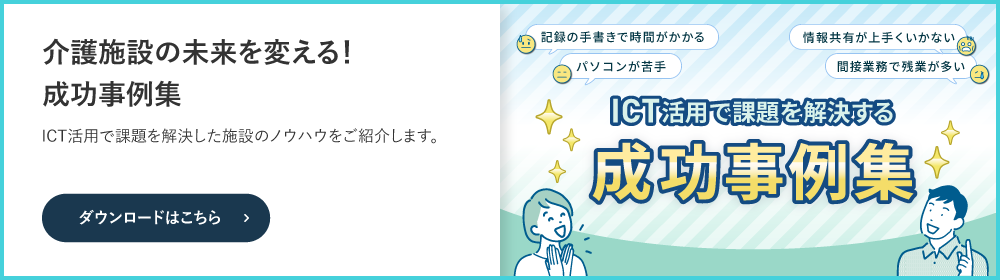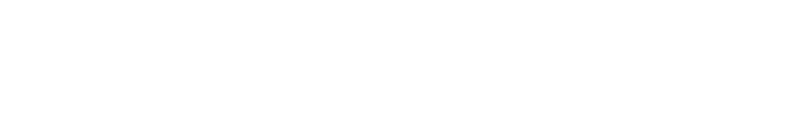
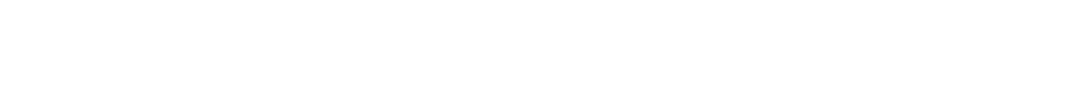
-
第13回 介護記録を書く・書かせるポイント
-
2025/05/15
-
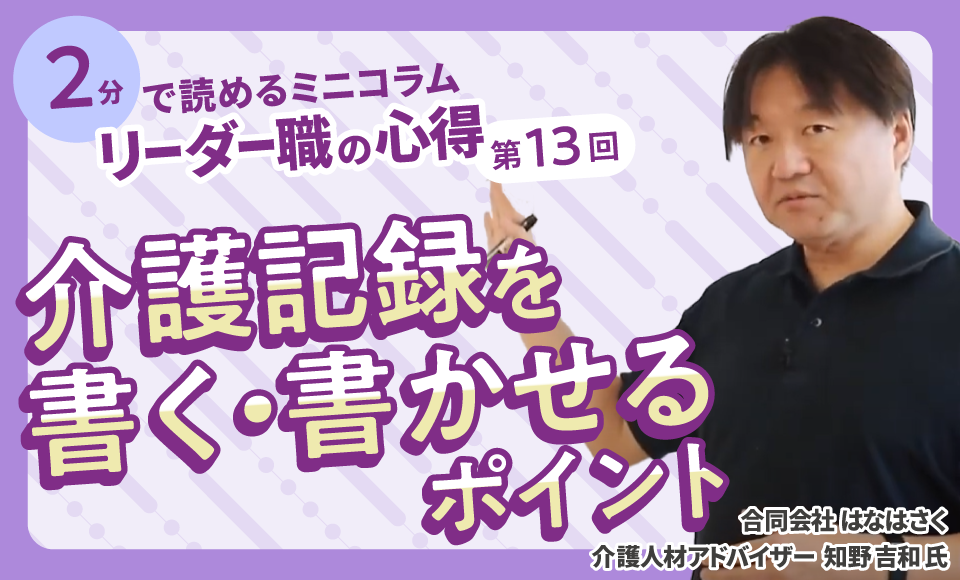
-
第12回はこちら: 第12回 会議の進め方と議事録の記載方法
「記録を書くのが苦手で…」「書き直しが多くて現場が回らない」――介護現場で頻繁に耳にするこの悩み。その背景には、記録の“表現力”以前に、根本的な力の不足が関係しています。今回は、介護記録を書く力を育てるために必要な視点と、リーダーができる現実的な教育方法についてお話しします。
介護記録に必要な力は、「専門用語の理解」と「国語力」
「介護記録を書くのが苦手」という声は、介護の現場では珍しくありません。実際に私自身、さまざまな施設を訪れる中で、記録の質や職員の記録力に悩む声を数多く聞いてきました。中には記録そのものに対して苦手意識を抱いてしまい、できれば避けたいと感じている方もいらっしゃいます。
では、介護記録を書くには何が必要なのでしょうか。記録の書き方や文章の形式ももちろん大切ですが、その前段階として身につけておくべき、もっと基本的な力があります。それが 「専門用語の理解」と「国語力(説明する力)」 です。
まず、専門用語について。介護や医療の現場においては、情報を的確に、かつ誤解なく共有することが非常に重要です。そのためには、曖昧な言い回しや個人の感覚に頼る言葉ではなく、定義がはっきりした専門用語を使う必要があります。かつて「専門用語を使わない記録を推奨しよう」という流れも一部にありましたが、実際の現場では、それでは情報共有の精度が下がってしまいます。プロとして他職種と連携しながら働くには、共通言語である専門用語を正確に理解し、適切に使うことが欠かせません。
次に国語力です。ここでいう国語力とは、文章を書く技術というよりも、「説明する力」「物事を筋道立てて伝える力」のことを指しています。私はこれまで、介護職員の方に小学校3年生程度の国語のテストを実施したことがあります。あくまで一例ではありますが、多くの方がこのテストで苦戦していたという事実があります。これはつまり、「文章をどう書けばよいか以前に、そもそも相手に分かりやすく説明する力が足りていない」状態だといえるのです。
同様に、専門用語に関する理解度テストも行ったことがありますが、こちらでも十分に答えられないケースが目立ちました。現場で「記録しておいて」と言われて戸惑う人が多い理由は、書き方が分からないというよりも、こうした基本的な言語力や用語の理解に課題があることが少なくありません。
したがって、介護記録を書くことに対する苦手意識を根本から解消するには、まず「書き方」を教える前に、「何を書くのかを理解できる力」や「それを説明する力」を育てることが必要です。そしてこの視点を、現場で職員を指導するリーダー層がしっかりと持っておくことが、組織としての記録力向上につながっていきます。
書き直しよりも“お手本”を。現場に合った教育の進め方とは
多くの現場で、記録の添削や赤ペンでの指導が当たり前になっています。「ここはこう書き直して」「この言葉では意味が伝わらない」といった指摘を繰り返しながら、何度も記録を書き直させているリーダーも少なくありません。
しかし実際には、このやり方がかえって非効率になるケースが多々あります。記録を書く力が十分でない職員に何度も修正を指示しても、元々の力が不足しているため、なかなか改善につながりません。むしろリーダーの負担ばかりが増え、現場全体の時間も取られてしまいます。
そこで効果的なのが、「お手本を示す」というやり方です。たとえば「誰々さんが転倒した」という場面で、職員が記録をうまく書けない場合、リーダーが本人から状況を聞き取りながら、代わりに文章を作成します。それを「この文章を参考にして、同じように書いてください」と示すのです。

この方法のポイントは、「真似ることが学ぶこと」だという考え方にあります。人は言葉も行動も、まずは他人の真似から学び始めます。「まねる」ことが「学ぶ」の語源であるように、正しい形を繰り返しなぞることで、少しずつ自分の力として身についていきます。
一方で、「とにかく自分で考えて書いてみて」という指導は、基礎力が育っていない人にはハードルが高すぎます。答えのない人に答えを出せと言っても、時間ばかりかかってしまうのです。だからこそ、最初からお手本を見せ、それを模倣してもらう。その繰り返しこそが、記録を書く力を育てる最も現実的で効率の良い方法です。
「そこまで丁寧にしなければいけないのか」と思う方もいるかもしれませんが、遠回りのようでいて、実はこれが一番の近道です。赤ペンで直し続けるよりも、時間も手間もかからず、職員の成長にもつながります。
リーダーの皆さんには、ぜひこの「お手本教育」の考え方を取り入れていただきたいと思います。それが、現場全体の記録力を底上げし、日々の業務を円滑に進める一歩となるはずです。
全13回を通してリーダー職の心得についてお話ししました。
ぜひ、ほかのコラムもご覧ください。
こちらもあわせてご覧ください。
当コラムは、掲載当時の情報です。

介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。