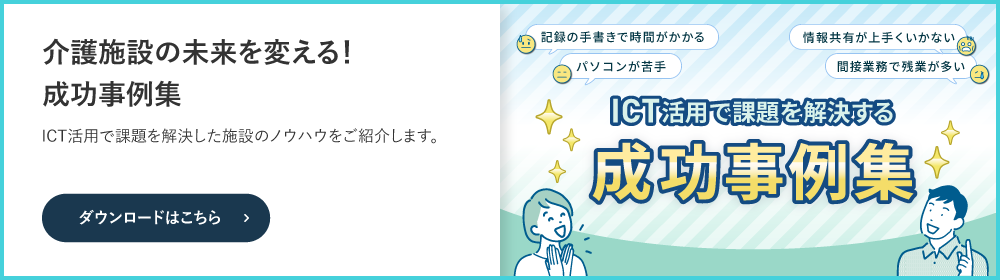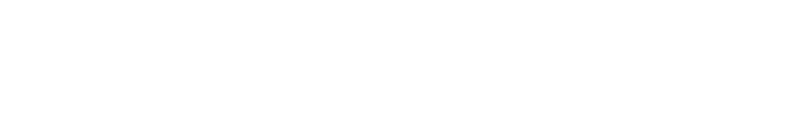
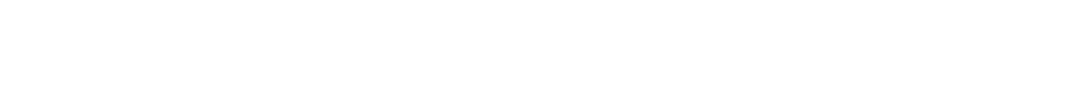
-
介護現場での接遇、実際の事例をご紹介!クレーム対応から定着までのポイント
-
2025/09/30
-

-
新人やベテラン、外国人スタッフなど、さまざまな背景のスタッフが働く介護現場では、スタッフごとに対応のばらつきが生じることも少なくありません。
- 他の施設ではどのような取り組みをしているのか知りたい
- 接遇を改善したいが、どう指導すれば良いかわからない
このような悩みを抱えている事業所も多いのではないでしょうか。
この記事では、介護現場で実際に行われた接遇の改善事例を紹介しながら、研修方法や接遇を定着させるためのポイントを具体的に解説します。利用者の満足度を高め、職員の働きがいにつなげる参考になる内容になっておりますので、ぜひ最後までお読みください。
介護現場での接遇とは?
接遇とは、相手に対して思いやりを持ち、適切な態度や言葉遣いで接することを指します。介護現場では、利用者一人ひとりの気持ちに寄り添い、尊厳を守りながら安心して過ごしてもらうためのコミュニケーション技術のことを指します。新人スタッフやベテラン・外国人スタッフなど、誰もが共通認識として持つべき介護現場の基本姿勢とも言えるでしょう。食事・排泄・入浴といった3大介護とともに、質の高いケアを提供するための大切な技術です。
接遇とは?介護接遇って何?おさえておきたい!介護現場での接遇・マナーの基本とNG行動介護現場での接遇の具体的な事例
実践が難しい接遇も、他施設の事例から学ぶことで改善のヒントが得られることもあります。ここでは、介護現場で実際に起った3つのケースを紹介します。
【ケース1】新人スタッフの対応あるある
新人Aさん: 利用者に対して
「〇〇ちゃん、お部屋戻るよー!さ、立って!」
親しみを込めているつもりでも、利用者をニックネームやタメ口で呼んでしまっていました。また、介助に集中するあまり、つい「〇〇するよ」という強い口調になりがちで、利用者を驚かせてしまうことがありました。
先輩スタッフ:
「Aさん、いつも頑張ってるね。一つだけ、利用者は人生の先輩だから『〇〇さん』って名前で呼ぶようにしましょう。介助の時も、Aさんのペースじゃなくて、利用者のペースに合わせて『次は〇〇しますね』と声をかけると、もっと安心してくださると思うよ。」
Aさんは指導を受け、丁寧な言葉遣いと事前の声かけを意識するようになり、数カ月後には利用者から「Aさんはいつも優しく声をかけてくれるから安心だ」と言われるようになりました。成功体験が自信につながり、Aさんの成長を促す良い循環が生まれました。
【ケース2】外国人スタッフの対応あるある
利用者さん:
「Bさんは、なんだか目を合わせてくれないわね…」
ベトナム出身のBさん。母国では、相手の目をじっと見ることが失礼にあたる場合があるため、つい視線をそらしてしまいがちでした。その文化的な背景を知らない利用者からは「そっけない態度だ」と誤解されていました。
先輩スタッフ:
「Bさん、いつもありがとう。日本では、相手の目を見て話すことが『あなたの話を真剣に聞いていますよ』という誠実さのサインになります。文化の違いで戸惑うと思うけど、少し意識してみると、利用者の方ももっと安心してくださるはずだよ。」
Bさんは文化の違いを学び、意識して利用者と目を合わせて話すようになりました。最初はぎこちなさがありましたが、日本人スタッフが「今の対応すごく良かったよ」と具体的に褒めることで、徐々に自信をつけました。もともとの性格もあって、今では利用者からも「Bさんは安心できる」と評判です。
【ケース3】利用者からのクレームに対応して改善した事例
ご家族:
「皆さん忙しいのは分かるんですが、日によってなんだか話しかけにくい雰囲気の時があって…」
特定の職員ではなく、事業所全体の「雰囲気」に対する意見でした。特に忙しい時間帯は、職員の表情が硬くなり、声のトーンも低くなるため、利用者やご家族が声かけをためらってしまう状況がありました。
管理者:
「ミーティングで出た意見をまとめると、忙しいときこそ一度立ち止まってにっこり口角を上げる。これをチームの統一ルールにしてみませんか?スタッフが笑顔でいることで事業所の印象が大きく変わるはずです。」
「声かけの前に口角を上げる」というシンプルなルールを全員で実践。さらに「挨拶を徹底する」など月ごとのテーマも決め、小さな改善を続けました。結果、事業所全体の雰囲気が和らぎ、顧客満足度調査でも「話しかけにくい」という意見がなくなりました。
介護現場で接遇が大切な3つの理由
ここでは、介護現場で接遇が大切にされている理由について、以下の3点を解説します。
- 1. 利用者の尊厳を守る
- 2. クレーム・トラブル防止になる
- 3. スタッフ間の信頼関係が向上する
ひとつずつ解説します。
1.利用者の尊厳を守る
介護は身体的な支援だけでなく、利用者の精神面を支える仕事でもあります。利用者は人生の先輩であり、どれだけ親しい関係であっても、ため口やニックネームは避けた方が良いでしょう。ほかにも、よかれと思った言動でも、本人を傷つけてしまうケースがあります。
- 「○○さん、排便が多量にありました」と食堂で大声で話す
- 本人の了解なしにサンタクロースやハロウィンの仮装をさせる
情報共有や行事を盛り上げるためとはいえ、こうした接遇の乱れは「不適切ケア」や「心理的虐待」へと発展する場合もあるため注意が必要です。
2.クレーム・トラブル防止につながる
接遇の乱れは利用者や家族の満足度に直結します。小さな不満でも、積み重なるとクレームやトラブルに発展する可能性があります。
例えば、面会時のあいさつや声かけがない、説明不足のまま介助を行うなどの対応を続けると「ぶっきらぼう」「雑に扱われている」と受け取られかねません。
逆に、笑顔で接したり、普段の様子を丁寧に説明したりすることの積み重ねが利用者からの信頼につながります。
3.スタッフ間の信頼関係が向上する
接遇は利用者だけでなく、職員同士の関係性にも影響します。スタッフ間で敬意を持った声かけや対応ができている職場は、チームワークが良く業務連携もスムーズです。逆に、乱暴な言葉遣いや不愛想な態度が蔓延していると雰囲気は悪化します。自分に向けられたものでなくても、高圧的な態度を見るだけで辛いものです。
接遇を意識することで、職員間のコミュニケーションも円滑になり、働きやすい職場づくりにもつながります。
これらのように、質の高い接遇は間接的に稼働率の安定につながり、ひいては職員が長く安心して働ける職場づくりに不可欠な土台となります。
介護現場接遇を定着させる5つの工夫
接遇を事業所に定着させるには、勉強会で学ぶだけではなく、身につけることが重要です。日々の業務で意識し続け、実践を繰り返すことで習慣になります。ここでは、現場に接遇を根付かせるための5つの工夫を紹介します。

1.チェックリストの活用
接遇改善の第一歩は現状を把握することです。「挨拶」「表情」「言葉遣い」など具体的な行動をリスト化し、自分自身の言動を評価します。まず管理者やベテランが率先して取り組むことで、全体の意識を高めます。ゆくゆくは指導できる人材を育成し、新人研修に組み込むことで、組織の文化として定着させていけるとよいでしょう。
2.ロールプレイ研修
知識を実践につなげるには、ロールプレイ研修が効果的です。「知っている」ことと「やったことがある」ことは大違いです。利用者役と職員役に分かれ、食事介助の声かけやクレーム対応など、具体的な場面を想定して練習します。高圧的な態度とていねいな態度の両方を体験することで、相手に与える印象の違いを学べます。また、スタッフの表情や態度、匂いが、想像以上に利用者に影響を与えていることにも気づけるでしょう。
3.定期的な振り返りで共通認識をつくる
研修効果を持続させるには、定期的な振り返りが欠かせません。虐待や身体拘束に関する委員会など、既存の委員会を活用しても構いません。月1回テーマを決め、ロールプレイで難しかった点や現場での成功事例などを共有し、チームの共通認識を深めます。
4.日常のフォローアップ体制
新しい取り組みを定着させるためには、繰り返し伝えることが大切です。事業所として接遇の底上げに取り組んでいくことを、朝礼や委員会、その他気づいたときに何度でも伝えていきましょう。スタッフが目にする掲示板を活用するのもひとつの方法です。また、「今日意識したい一言」を共有したり、良い対応を見かけたときにその場で褒めることで、スタッフ全員が前向きに取り組みやすくなります。
5.表彰制度による動機付け
モチベーション維持のためには、評価と承認も欠かせません。対応の良いスタッフを表彰したり、利用者からの感謝の声を全体で共有したりするなど、努力が形になる仕組みを作ると、スタッフのやる気向上につながります。
まとめ:介護現場に接遇を定着させて、サービスの質を高めよう
本記事では、介護現場における接遇の重要性から具体的な事例、研修方法や定着までの工夫などについて解説しました。接遇の向上は、利用者の満足度と職員の働きがいを高め、事業所全体の質を底上げします。日々の記録や職員間の情報共有を効率化し、こうした組織的な取り組みをサポートする介護ソフトにご興味のある方は、ぜひNDソフトウェアへお問い合わせください。
介護・医療経営の専門家が最新のヘルスケア情報を毎月ご提供しています。お申し込みはこちら
介護事業者さまの現場をサポートする「ほのぼのNEXT」は、事業所様の運用に合わせて機能を選んでご使用いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。